子どもと猫は同居できる?猫の飼い始めに適した子どもの年齢や飼う時の注意点

「猫を飼い始めてから、子どもとうまく同居ができるかな」
そんな時、猫を飼い始めてから問題が起きたらと心配ですよね。
実は、猫を飼う前に心配事の対処法を知っていれば安心です。
本記事では、子どもと猫が同居するのに適した年齢や、飼う前に気をつけたいことを紹介します。

猫を飼い始めてから、子どもとうまく同居できるか心配で踏み出せない方は、参考にしてくださいね。
子どもと猫は同居できる?
 そもそも子どもは猫と同居できるのでしょうか?
そもそも子どもは猫と同居できるのでしょうか?
子どもと猫との同居で、飼う時に気をつけたい注意点が2つあります。
- 乳児の場合は衛生管理などが必要
- 子どもが3〜4歳になると猫を迎えやすくなる
詳しく説明します。
1. 乳児の場合は衛生管理などが必要
乳児がいる家庭で猫を飼う場合は、衛生管理などが必要です。
なぜなら、乳児はまだ免疫力が弱く、感染やアレルゲンの原因になることがあるからです。
たとえば、猫にノミやマダニが寄生していた場合、乳児に病気を媒介してしまうことも。
したがって、乳児がいる場合は、猫を飼う際には衛生管理を徹底する必要があります。
2.子どもが3〜4歳になると猫を迎えやすくなる
子どもが3〜4歳になってからなら、猫を迎え入れやすくなります。
なぜなら、3〜4歳は猫と一緒に遊んだり、コミュニケーションをとったりできる年齢だからです。
自分で身の回りのことや言われたことを理解でき、やりたい気持ちや好奇心も満ちてくるので、「世話をしたい」と思える可能性もあります。
子どものいる家庭でいつ猫を迎え入れるべきか迷ったら、3〜4歳を目安にするといいでしょう。
子どもと猫を同居させるメリット
 子どもと猫を同居させると、どんなメリットがあるのでしょうか?
子どもと猫を同居させると、どんなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットは4つあります。
- 責任感が湧く
- 思いやりの気持ちが育つ
- 命の大切さを知れる
- 癒しになる
詳しく説明します。
1. 責任感が湧く
子どもと猫を同居させるメリットは、責任感や思いやりの気持ちが芽生えることです。
なぜなら、「家族の一員として守ってあげなければ」という思いが、猫に対する優しさや責任感に繋がるからです。
たとえば、子どもは猫にごはんをあげたりトイレを掃除したりブラッシングをしたりと、日々お世話をすることで責任感が湧いてきます。
このように、責任感が湧くことは、子どもと猫を同居させるメリットだと言えます。
2. 思いやりの気持ちが育つ
自分より小さい猫の世話をすることで、思いやりの気持ちが育ちます。
なぜなら、猫を通して生き物に愛情を持って接することの大切さを学べるからです。
たとえば、猫が体調を崩してしまったら、子どもは「大丈夫かな?」と心配するでしょう。
したがって、猫との同居を通して思いやりの気持ちが育つことは、子どもの情緒面にもよい影響を与えます。
3. 命の大切さを知れる
子どもと猫を同居させるメリットとして、命の大切さを知れることも挙げられます。
猫との同居で命が永遠に続くものではないことを知り、大切さを知るからです。
たとえば、猫は誰かが世話をしなければ、生きていけません。
また、愛情を持って世話をしていても、病気や高齢になり猫が亡くなってしまうことも。
子どもは猫と同居をすることで、避けては通れない出来事を通して、命の大切さを学べます。
4. 癒しになる
猫との同居は、子どもにとって癒しになります。
なぜなら、猫は子どもが落ち込んだり、辛い思いや悲しい思いをしたりした時、心のより所になってくれるからです。
たとえば、猫の仕草をみたりなでたり抱いたりすることで気持ちが落ち着き、心の中にある不安や怒りなどの気持ちを軽減できます。
したがって、猫との同居は子どもに癒しを与えてくれます。
子どもと猫を同居させる場合の注意点
 子どもと猫を同居させるにあたっては、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?
子どもと猫を同居させるにあたっては、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?
4つの注意点があります。
- 猫の扱い方を子どもによく伝える
- 事前にアレルギー検査をする
- 猫の爪を切る
- ブラッシングをこまめにする
詳しく説明します。
1. 猫の扱い方を子どもによく伝える
子どもと猫を同居させる際の注意点は、猫の扱い方を子どもによく伝えることです。
なぜなら、猫は生き物であり、子どもの思いどおりに行かないこともあるからです。
たとえば、猫はどんなに可愛くても、嫌なことをされればシャアーと威嚇して怒ることもあります。
このように、猫を迎え入れるにあたっては、子どもに扱い方をよく伝えることが大切です。
2. 事前にアレルギー検査をする
猫を飼う前に心配な方は、事前にアレルギー検査をすると安心できます。
なぜなら、子どもに猫アレルギーがある場合、猫を飼うのが難しくなる可能性があるからです。
たとえば、以下のような症状が出た場合は猫アレルギーが疑われます。
- 目がかゆくなる
- まぶたが腫れてくる
- 目の充血や、涙がでる
- 皮膚が赤くなったり、かゆみがでる
- 咳がでたり痛み
- 鼻水がでる
- 喘息を引き起こす場合もある
したがって、アレルギー検査をすることで、事前に対処法も検討できます。
アレルギーがあるから猫を飼えない場合もありますが、軽度の場合は気をつけることで軽減できるでしょう。
3. 猫の爪を切る
猫の爪は鍵上に曲がっていて先が鋭くとがっているので、定期的な爪きりのケアは必要です。
なぜなら、爪を定期的に切ることで、怪我を防げるからです。
たとえば、感染症で「ねこひっかき病」にかかることもあるので、短く猫の爪を切り防ぎましょう。
爪を切る際は、猫の爪先のとがった部分、血液の流れていない透明な部分を切ります。
爪がうまく切れない場合は、爪先1〜2㎝きるだけでもよいので、こまめに伸びてきたら爪切りをするとよいです。
猫の爪を切ることで、子どもが誤って引っかき傷をつくり怪我をしたりすることを防げます。
4. ブラッシングをこまめにする
ブラッシングをこまめにすることで、猫の抜け毛を減らせます。
なぜなら、抜け毛によってはフケやダニなどがアレルギーの原因になることもあるからです。
猫にブラッシングをすることは、マッサージ効果もあり、皮膚病・怪我・ノミなどの寄生がないかを気をつけることも。
このように、子どもは猫のブラッシングを通して世話をすることで、ふれあえるためスキンシップが深まります。
まとめ
 猫との同居を考えるにあたっては、子どもと同居できるのか不安ですよね。
猫との同居を考えるにあたっては、子どもと同居できるのか不安ですよね。
子どもにとって家族以外の猫との生活は、責任感や他者に対する優しさが育まれるなど、たくさんのメリットがあります。
この記事では、猫との暮らしで子どもが適した年齢や、飼う前に気をつけたい注意点を紹介しました。
ぜひ本記事を参考にして、猫との暮らしを楽しんでくださいね。


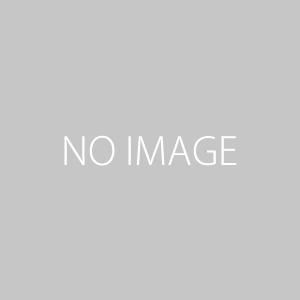







この記事へのコメントはありません。