子供の友達関係でトラブル!見抜き方や親の介入は?どう対応すべき?
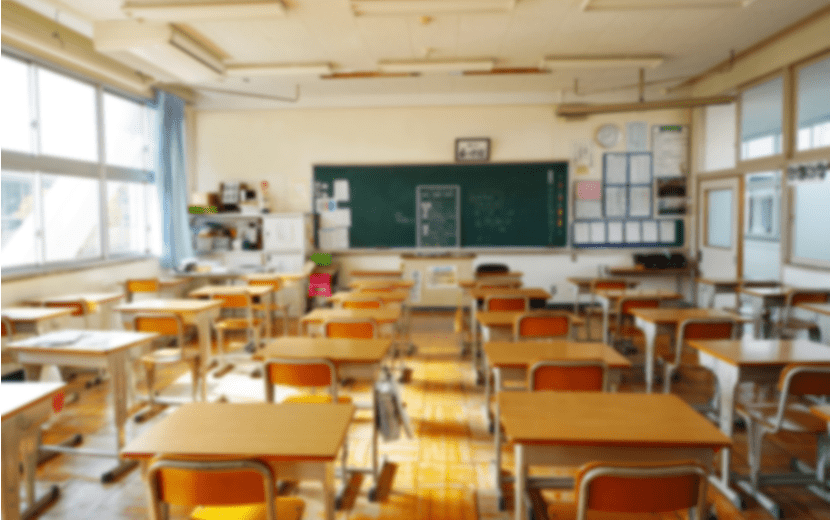
小学生になると子供同士で遊ぶことが増え、友達関係でのトラブルも起きやすくなります。
しかし、親がどうサポートすればいいかわからないことも。
本記事では、家族支援カウンセラーの筆者が、友達とトラブルを抱えた子供の出すサインや、親が取るべき行動について紹介します。
子供の友達トラブルでお悩みの方はぜひ参考にしてください。
見逃さないで!友達とのトラブルを抱えた子供が見せるサイン8つ
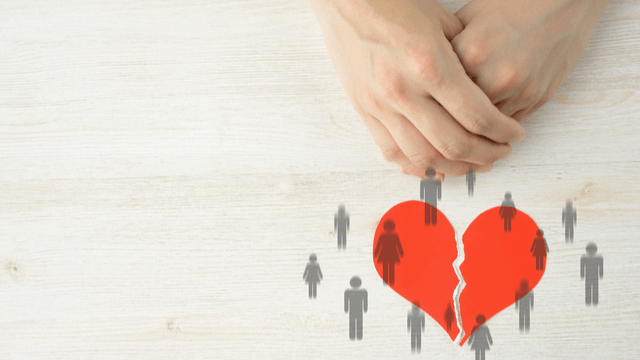
友達とのトラブルを抱えた子供は、どんなサインを見せるのでしょうか?
サインは主に8つあります。
- いつもより元気がない
- 普段は話す学校のことを話さない
- イライラして反抗的になる
- 学校に行きたがらない
- 下校が早く放課後遊ばない
- よく物を壊す・なくす
- 子供が買い与えた覚えのない物を持っている
- 怪我をしている
詳しく説明していきます。
いつもより元気がない
友達とのトラブルがあると、子供はいつもより元気がなくなる傾向があります。
子供なりに悩んだり、落ち込んだりしているサインだと言えます。
たとえば、いつもと比べて元気がない日が続くなら、学校で何かトラブルに巻き込まれているかもしれません。
「いつもより元気がない」というのは、最初のSOSサインだと言えます。
普段は話す学校のことを話さない
学校であったことをいつも話してくれるのに、急に話さなくなることもトラブルのサインです。
子供は、トラブルがあっても「ママに心配をかけたくない」「親に言ってもムダ」などと思っている可能性があります。
この場合、無理やり聞き出そうとすると、かえって口を閉ざしてしまうでしょう。
イライラして反抗的になる
子供によっては、友達とのトラブルを抱えると、急にイライラしたり反抗的な態度を取ったりすることも。
友達関係がうまくいかないことへの苛立ちを、親にぶつけているのです。
たとえば、友達とけんかをしたり、何か理不尽なことを言われたのに言い返せなかったりすると、親に反抗的な態度を取ってしまうことも。
「友達と何かあったの?」など、核心をつく質問をしてしまうと、かえって反抗が悪化することもあります。
学校に行きたがらない
学校に行きたがらないのも、友達とのトラブルを抱えた子供が見せるサインの一つ。
学校に自分では解決できないトラブルがあると、登校が億劫になるためです。
また、友達関係のストレスから、頭痛や腹痛など「身体のSOSサイン」が現れることもあります。
この場合、親に心配をかけたくなくて「行きたくない理由」はなかなか言い出せないことが多いでしょう。
下校が早く放課後遊ばない
放課後誰とも遊ばず、まっすぐ帰ることが続いたら、何かトラブルがあるかもしれません。
放課後遊ぶ友達がいなかったり、トラブルから逃げようとしたりして、早く下校することがあります。
いつも一緒に遊んでいた友達とけんかをしたり、仲間外れにされている可能性も。
この場合、子供の様子を注意深く観察する必要があるでしょう。
よく物を壊す・なくす
よく物を壊したりなくしたりする場合も、友達関係のトラブルが関与しているかもしれません。
友達に物を壊されたり、隠されている可能性が考えられるからです。
「どうして壊したの?」と本人のせいにして叱らずに、「何があったのか」をしっかりと確認しましょう。
子供が買い与えた覚えのない物を持っている
買い与えた覚えのない物を子供が持っている場合も、注意が必要です。
友達の物を取り上げたり、友達と万引きをしたりした可能性があります。
頭ごなしに叱る前に、まずは冷静にどこで手に入れたのかを聞き出しましょう。
怪我をしている
怪我も友達とのトラブルを抱えた子供が見せるサインの一つです。
「怪我=いじめ」と断定はできませんが、何らかのトラブルに巻き込まれている可能性があります。
原因が我が子にある場合もあるので、感情に任せず、冷静に対処しましょう。
【被害者・加害者別】子供の友達間トラブルに親は介入する?適切な対応

子供の友達関係のトラブルに、親は介入すべきなのでしょうか?
適切な対応を、被害者・加害者別に紹介します。
- 親が介入すべきものとそうでないものがある
- 我が子が被害者の場合にすべき対応
- 我が子が加害者の場合にすべき対応
順に詳しくみていきましょう。
親が介入すべきものとそうでないものがある
そもそも子供の友達関係のトラブルには、親が介入すべきものとそうでないものがあります。
すべての問題に親が介入してしまうと、子供の「自分で問題を解決する能力」を奪うことになるためです。
しかし、以下のような深刻なトラブルがあった場合は、早めに親が介入し、適切な対処をする必要があります。
- 大きな怪我をして帰ってきた
- 持ち物を取られた
- いじめで精神的に追い詰められた
- 万引きなど犯罪を強要された
親が介入すべきかは、トラブルの内容によって異なります。
適切な対応に迷った場合は、まずは学校に相談し、冷静に対処するといいでしょう。
我が子が被害者の場合にすべき対応
我が子が被害者の場合、まずは本人に事情を聞き、子供達だけで解決できそうであれば見守りましょう。
感情的にならず冷静に対応しつつ、傷ついた子供の心のケアをしてあげることが大切です。
しかし、我が子の話を一方的に信じてしまうと、事の真相が見えてこないことも。
以下は、我が子が被害者の場合に、親がすべき対応の一例です。
| トラブルの内容 | 親がすべき対応例 |
| 怪我をした |
|
| 持ち物を取られた |
|
| いじめられた |
|
| 犯罪を強要された |
|
見守る場合も介入する場合も、感情的にならず、冷静に対応しましょう。
我が子が加害者の場合にすべき対応
我が子が加害者側の場合、まずは感情的にならず、経緯を本人に説明させましょう。
トラブルの内容や経緯を知らないと、親がすべき行動を判断できないからです。
怪我やいじめの加害者だった場合は、理由はどうであれ相手を傷つけたことは事実なので一刻も早く、被害者本人と家族に謝罪しましょう。
万引きなどの行為を強要した場合は、年齢に関わらず「犯罪」であるという事実を理解させましょう。
もし弁護士に相談したい場合は、国によって設立された「法テラス」という制度があります。
トラブルの内容に応じて、法制度や相談窓口を無料で案内してくれるので、いざというときは相談してみるといいでしょう。
(参考URL:法テラス)
まとめ

友達間のトラブルは、成長する過程で誰にでも起こり得ることです。
本記事では、友達とトラブルを抱えた子供の出すサインや、親が取るべき行動を紹介しました。
子供を信じて見守ることが大切ですが、親の介入が必要な場合は、冷静な対応を心がけましょう。
本記事が、お子さんのトラブル解決の何らかのヒントになれば幸いです。










この記事へのコメントはありません。